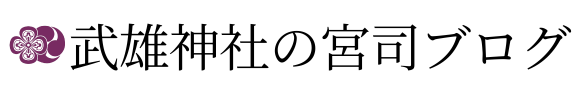本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
武雄神社の宮司(ぐうじ)、岩田孝夫(いわた たかお)と申します。
武雄神社は愛知県武豊町に鎮座し、この町と深い関わりをもつ神社です。
今から約150年前、この地域には「長尾村」と「大足村」という、二つの村がありました。
その後、二つの村が合併し、新たに「武豊町」が生まれました。
この「武豊」という町名に武雄神社は関わっています。
当時の長尾村には武雄神社、大足村には豊石神社がそれぞれ鎮座していました。
この二つの神社それぞれの頭文字「武」と「豊」を一文字ずつ取り、「武豊町」と名付けられます。
このように武雄神社は武豊町のはじまりに関わっていたのです。
私の家系である岩田氏も武豊町との縁がございます。
鎌倉時代中期、私の祖先がこの地に長尾城を構え、そのお城の守り神としてお祀りしたのが武雄神社です。
(※詳しくは武雄神社についてをご覧ください)
岩田氏はその頃から武雄神社をはじめ、町内の各神社に奉仕してまいりました。
私は30代目として、この務めを引き継いでおります。
ご縁があってご覧いただいておりますので、ここで少し神主の役割をご紹介いたします。
神主として
神主の仕事とは、大神様と人々の間に立ち、仲を取り持つこと。
即ち「なかとりもち」です。
日々のお祭りやお祓い、ご祈祷を通して参拝者の皆さまの心と対話して「人には元気で清らかで穏やかな日々」「町には溢れる活気」をもたらすこと。
これが神主の一番の役割です。
しかし悲しいことに近年、ご近所どうしの繋がりが弱くなったと言われています。
日々の暮らしが便利になり、SNSの普及で人との関わり方が変化したこともありますが、私たち神主が責務を十分に果たせていなかったという反省もございます。
だからこそ、神社にできることは、まだまだある!
たとえば、武豊町の春の大祭り「しゃんぎり祭り」では、6輌の御山車(おくるま)が各組で引き継がれてきた勇囃子(いさみばやし)を奏でながら境内に集まります。
そのときに天高くつき上げられる「梵天(ぼんてん)」を見ていると、私には昔の人たちの「町の誇りを繋げていきたい」という願いが聞こえてくるのです。
私はその願いに応えるべく、参拝者の皆さまや町民・区民の皆さま、そして子どもたちに地域のつながりや伝統を身近に感じてもらえるよう努めてまいります。
神道では今この時、この瞬間を現在とは呼ばず「中今(なかいま)」と呼びます。
過去と未来の間にあたる時間であることから、そうした漢字が当てられたとも言われています。
この言葉は、私たちに問いかけます。
「先人が築いたものを、どう未来に繋ぐのか」
先代の宮司もよく「祖先たちは目の前のお祭りだけではなく、その先にある町の姿にも心を向けてきた」と話しておりました。
そうした想いの積み重ねがあったからこそ、武雄神社をはじめ、町内の各神社が今日まで大切に受け継がれてきたのだと感じております。
私もまた神主としてその想いを受け継ぎ、できることをひとつずつ丁寧に重ねながら、次の世代に引き継ぎたいです。
武豊町民の一人として
武豊町の未来と向き合うこと。
それは町民の一人である私自身の想いでもあります。
自分の子どもたちが私と同じくらい武豊町を好きになり、町を誇りに感じる大人になってほしい。
そして子どもたちが親になったとき、私と同じような想いを子どもに伝えてほしい。
私はそう願っています。
『町を想う心を次の世代へ繋げる』
今、目の前にある課題を解決するのも、もちろん大切です。
しかし、それ以上に大切なのは、未来を担う子どもたちの心に「町を大切に思う気持ち」を宿すこと。
それこそが、町の真の繁栄へと繋がると確信しています。
私は武雄神社の宮司として、そして一人の町民として『武豊町愛』を繋げられるよう取り組んでいきたいと思います。
皆さまへ
このブログでは神社内外でのお祭りや行事だけでなく、私の知っている武豊町の歴史、日々の気づきなどを書いていく予定です。
難しい話ではなく、子どもでも読めるような、わかりやすい表現を心がけます。
神社は昔から人々の暮らしに根ざしてきた場所です。
そしてこれからも、武豊町にとって武雄神社は欠かせない存在であり続けると信じています。
武雄神社をはじめ、町内の各神社を通して、武豊町をもっと好きになってくれる人が増えたらうれしいです。
そして、その想いが次の世代へと広がっていくことを、心から願っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。