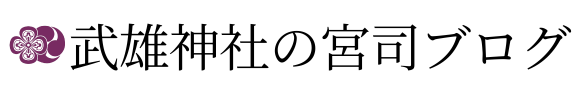武雄神社についてお話しています。
ホームページでお伝えしきれなかった部分を中心にご紹介します。
由緒と社格
武雄神社は、愛知県知多郡武豊町に鎮座する神社です。

鎌倉時代中期に私の祖先である岩田氏によって長尾城の領内・城内鎮護の社として祀られました。長尾城を築いて以降、累代の社家として岩田氏が武雄神社の職務を務めてきました。
日本には「近代社格制度」という仕組みがあります。
神社の歴史や由緒、地域における重要性などをもとに、社格(しゃかく)という等級を定める制度です。
武雄神社は由緒ある歴史と地域からの崇敬が評価され、明治5年(1872年)に村社、昭和15年(1940年)には郷社へと昇格。
戦後、神社本庁のもとで七等級に分類されましたが、昭和30年(1955年)4月に愛知県神社庁より四等級(旧国幣小社格相当)に指定されました。
知多半島において、最も高い社格を持つ神社でございます。
ご祭神とご利益
武雄神社の主祭神は、須佐之男命(すさのおのみこと)。
天照大御神の弟神として知られ、勇ましい神様という印象が強いかもしれませんが、その本質は「災いを断ち、福を招く」存在です。
厄除けや勝負運、さらには家内安全を願う方々に広く信仰されてきました。
この須佐之男命を中心に、武雄神社の本殿には合わせて九柱の神々が合祀されています。
右扉に五柱の神様、中扉には主祭神である須佐之男命、左扉には三柱の神様です。
右扉の五柱の御祭神とご利益
一.品陀和気命(ほんだわけのみこと):子孫繁栄、学業成就
二.神功皇后(じんぐうこうごう):安産、子宝、開運
三.大己貴命(おおなむちのみこと):良縁、家内安全
四.櫛名田比売命(くしなだひめのみこと):夫婦円満、女性の守護
五.少彦名命(すくなひこなのみこと):病気平癒、健康長寿
中扉の御祭神とご利益
須佐之男命:厄除けや勝負運、家内安全 ※武雄神社の主祭神
左扉の三柱の御祭神とご利益
一.弥五郎殿命(いまたねつぐのみこと):地域の繁栄、土地の安全
二.天児屋根命(あめのこやねのみこと):学問
三.天宇受売命(あめのうずめのみこと):芸能
このように武雄神社の本殿だけでも九柱の御祭神をお祀りし、さまざまなご利益をお頒かちいただけます。
また、摂社である長尾七宮社には、七柱の神々が鎮まっております。
長尾七宮社の御祭神とご利益
一.大山祗命(おおやまづみのみこと):交通安全
二.豊受姫命(とようけひめのみこと):五穀豊穣、商売繁盛
三.日本武命(やまとたけるのみこと):勝運、交通安全
四.菅原道真公(すがわらのみちざねこう):学業成就
五.菊理姫命(くくりひめのみこと):縁結び、夫婦和合
六.火結乃命(ほむすびのみこと):火難除け
七.大物主神(おおものぬしのかみ):商売繁盛、病気平癒
武雄神社、そして摂社の長尾七宮社のそれぞれの神様は異なるご神徳を持ち、人生の節目や悩みごとにそっと力を貸してくださる存在です。
参拝された方からは「清々しい気持ちです」「ご縁に恵まれた」などのお声をよくいただきます。
私自身も神様の力が人と人とを結び、支え、癒してくださっているのだと、日々感じています。
境内(けいだい)
鳥居をくぐると、まず目に飛び込んでくるのが、こちらの常滑焼の陶製狛犬。

昭和初期に奉納されたもので、艶やかな質感と愛嬌ある表情が特徴です。
陶器の狛犬は全国的に珍しいので、足を止めてくださる参拝者さまも多く「こんな狛犬は初めて見ました」と声をかけられることもしばしば。
奥へと進むと「御井戸(みいど)」と呼ばれる澄んだ井戸があります。

古来より神事にも用いられてきた御神水が湧き出ており、そばには小さなお社「御井社」も祀られています。柄杓で水をすくい、手を清めながら願いを込める姿には、自然と背筋を正すような清らかさがあります。
境内の艮(うしとら=北東)の方角には、樹齢100年を超える御神木の柊(ひいらぎ)が根を張っています。葉にある棘が邪気を払うとされ、鬼門除けとして重んじられてきました。

私自身も幼いころからこの柊のそばを通るたびに、なんとも言えない安心感を覚えていたのを今でもはっきりと覚えています。
派手さはございませんが、静けさの中に歴史が息づいているのを感じていただけるはずです。
お祭り
武雄神社では、四季を彩るお祭りも大切に受け継いでおります。
春の例祭「しゃんぎり祭り」は、毎年4月15日に最も近い土曜・日曜に行われる、武豊町を代表するお祭りです。

6つの区内から御山車(おくるま)が武雄神社に集まり、勇壮に並ぶ光景はまさに圧巻。からくり人形や迫力ある勇囃子(いさみばやし)が響き渡り、お祭り一色に染まります。
法被姿の大人たちと子どもたちが真剣な眼差しで御山車を引く姿からは、世代を超えて受け継がれる地域の絆が伝わってきます。
秋の「名月祭」は、中秋の名月の夜に執り行われる幻想的な祭典。
境内には篝火が灯され、森の木々が月明かりに照らされる光景は、まるで時間が止まったかのような静けさと美しさに包まれます。朗読や音楽の奉納が行われる中、参拝者の皆さまもそれぞれの想いで月を見上げ、秋を感じておられます。

かつてこの地域では文人や歌人が神社に集い、満月を愛でながら和歌を詠む風雅な集いが催されていました。これがいつしか「月詠みの森」と呼ばれ、地域に根付いていきました。
そうした風情と文化を受け継ぎながら、現代の名月祭は「武雄神社から望む月」として日本百名月第56号にも認定され、文化的・観光的にも高い評価を得ています。
どちらのお祭りも神様への感謝、そして地域のつながりを感じられる貴重な時間です。
町民・区民の方々が準備に取り組む姿を見るたびに、伝統を守る力と次の世代に受け継ぐ意志の大切さを感じております。
グルメ・お土産
武雄神社の参拝のあとは、町内の味や名物にもぜひ触れてみてください。
武豊町は知多半島の穏やかな海に面しており、新鮮な魚介を活かした料理や地元で親しまれている「しらす丼」などが楽しめます。漁港の近くには、とれたばかりの海の幸を味わえる食事処もあります。
昔ながらの醸造文化も息づいており、たまり醤油や味噌などの伝統的な調味料も名産です。
参拝の記念に、ぜひ地元ならではの味と心をお持ち帰りください。
また、例祭・名月祭などの恒例祭典では、武雄神社の御神田で作った古代赤米のいなり寿司もございます。

タイミングがあえば武雄神社名物「赤米いなり寿司」もご賞味ください。
お気軽に足をお運びください
武雄神社は、永き古い深き歴史をもつ神社です。
しかし決して、敷居の高い場所ではございません。
日常の中でふと立ち寄りたくなるような、そんな場所だと私は思っています。
風の音に耳をすませたり、木々のざわめきを感じたり。
忙しい日々の中で、少し立ち止まるきっかけになれたら嬉しいです。
「武雄神社に行ってみようかな」
そう思ってくださった時には、お気軽に足をお運びください。
そして、もし境内で私を見かけたら、どうぞ私に声をかけてください。
参拝者の皆さまからお声をかけていただくたびに、私自身も多くのご縁に支えられていることを実感いたします。
武雄神社で、皆さまとのご縁を心よりお待ちしております。
アクセス
住所:愛知県知多郡武豊町上ヶ8
電車:「JR武豊駅」から北へ徒歩約3分、「名古屋鉄道・上ゲ駅」から約5分
お車:神社北側の境内の中にございます「参拝者駐車場」にお停めください